「NQC探索型プログラム」 が育む未来の量子人材ネットワーク ~若手量子技術研究者が語るNQCの「魅力」と「課題」
レポート
活動報告
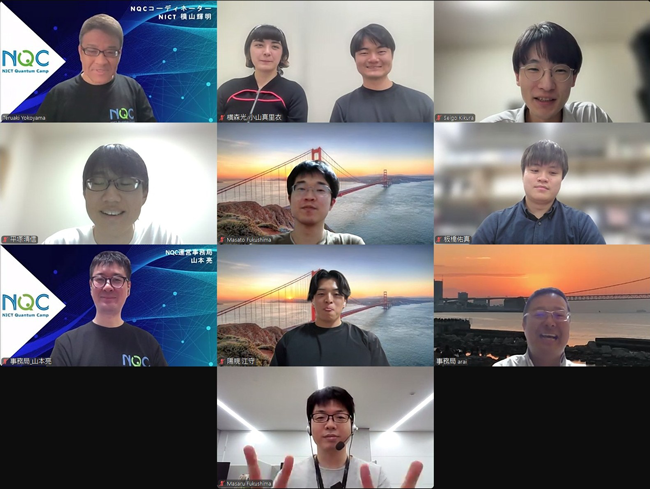
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)は、2020年度より「量子ICT人材育成プログラム(NQC)」を実施している。本プログラムは、量子計算や量子通信といった先端技術分野において、依然として人材が不足している現状を踏まえ、これらに精通した研究者やエンジニアの育成を目的として設けられたものである。
プログラムは大きく二つのタイプに分かれている。ひとつは、量子技術に関心を持つ者に対し入門的に幅広い知識を身につけることを目指した「体験型」である。もうひとつは、資金的支援を受けながら本格的に量子技術の調査、研究、開発に取り組む「探索型」である。
今回の座談会には、この「探索型」に参加し、大学院や企業に所属しつつ量子技術の研究に邁進している7名がオンラインにて集まった。量子技術と深く関わる研究者としての視点から、NQCプログラムの魅力、ならびに実際に取り組んでいるからこそ見えてくる改善点について、率直な意見を述べてもらった。
聞き役はNICT主任研究員の横山輝明氏が務め、また2020年に「体験型」プログラム、2021年に「探索型」プログラムに参加した北海道大学大学院情報科学院/理化学研究所数理創造研究センターの江守 陽規氏も加わり、自身の経験も踏まえ参加者に質問を投げかけた。 (文・構成:カトウワタル)
<プロフィール>
横山 輝明
国立研究開発法人情報通信研究機構 量子ICT協創センター 主任研究員
江守 陽規
北海道大学大学院情報科学院/理化学研究所数理創造研究センター
板橋 佑真
慶應義塾大学大学院理工学研究科
木倉 清吾
早稲田大学理工学術院先進理工学研究科
平塚 晴信
中央大学理工学研究科電気電子情報通信工学専攻
横森 光
慶應義塾大学政策メディア研究科
小山 真里衣
慶應義塾大学環境情報学部
福島 誠人
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻
渡邉 悠稀
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻
さまざまなバックグランドからNOQ 「探索型」プログラムに参加
横山:本日はよろしくお願いします。まずは皆さんの自己紹介と、4月からの状況を教えてください。
横森:慶應義塾大学のロドニー・バンミーター研究室に所属している修士1年の横森です。今は主に3つのプロジェクトに関わっています。NQCでやらせていただいたディスティメーションを先日QCに出させていただいて結果待ち、というのが1つと、もともと修士でやっているのは、イオントラップ用の光フリップチップのファブをやっています。それに加えて量子インターネットワークにおける光スイッチチップのファブの 「永山ムーンショットプロジェクト」 にも携わっています。
小山:同じく慶應義塾大学のバンミーター研究室に入っている学部生4年の小山です。NQCを始めた当初は沖縄科学技術大学院大学(OIST)のインターンで量子リピーターの研究を行っていました。今はNQCでも行ったディスティメーションの研究と、横森さんと同じ光スイッチファブの研究を始めました。

板橋:板橋です。慶應義塾大学の早瀬研究室の修士2年です。研究テーマもNQCの時と変わらずダイヤモンドNV量子センサーという量子センサーを使って、主にマイクロメートルサイズの微小回路の温度と交流位置場の同時イメージングを研究しています。

木倉:木倉と申します。早稲田大学の理工学術院青木研究室の博士2年です。NQCでは、共振器量子電磁力学系を用いた光と原子のゲート操作の理論提案を掲げていまして、現在も引き続きその研究に取り組んでいます。

福島:福島です。東京大学大学院理学研究科物理学専攻の井手口研究室の博士1年です。研究内容はあまりこのプログラムとは関係なくて、分光イメージングというものをやっています。それと並行して、NQCでの研究テーマでもあった測定型量子計算のコンパイラの開発をしています。

渡邉:渡邉です。東京大学理学系研究科の柏にある岡研究室 博士課程1年です。生体内化学反応ネットワークを古典確率過程として捉えて制御する手法を理論的に構築したいというモチベーションで、時間周期的な駆動の物理を扱っています。NQCでのテーマは福島君と佐々木君と同じチームで実装をしていました。現在はFTQCコンパイラの作成に向けてサーベイをしているという段階です。

平塚:平塚です。中央大学理工学研究科の電気電子情報通信工学専攻 松崎研究室所属の修士2年です。NQCでは、KPOを用いた量子アニーリング中の断熱条件の測定法という研究を行い、現在も続けています。

より多くの人との交流や、自分の研究以外の分野について学びたい ― NQCプログラムへの期待
横山:次に、このプログラムをどうやって知ったのか、またどうして応募しようと思ったのかというきっかけや、参加前に抱いていた期待について教えてください。
横森:最初に知ったきっかけは講師でもあるロッド先生からの告知です。期待していたことは、普段は身内からのフィードバックだけになってしまうので、外の人からのフィードバックを得られたり、コネクションを拡大したりしたいと思っていました。個人的に印象に残っていたのは、中間発表で特に佐々木先生がすごくたくさんフィードバックをしてくれて、発表に専念できるという意味で、良い経験ができたと思っています。
小山:それに付け加えて、身内だけだと量子ネットワーック関連だけになってしまうので、他の人たちがどんな研究を行っているのか、ほかにどんな分野があるかという興味もありました。私もいろんな専門家の方からフィードバックをもらえたので、より研究も進められ、テーマもさらに詳しく絞ることができて、すごく良い経験になりました。
木倉:知った経緯は正確に覚えてないのですが、2年ぐらい前に報告会をネットで知ったのがおそらく最初だと思います。実験の研究室に所属しており、理論研究の議論を行う機会が限られているため、NQCを通じて自分の研究の議論ができることを一番のモチベーションにして申し込みました。実際に参加したところでは、中間報告の際に佐々木先生に興味を持っていただいて、いろいろご意見いただけたのが印象に残っています。佐々木先生からは具体的にこういうことに使えないのかといったご提案もいただいて、新しいインスピレーションが生まれる機会になったと思います。
平塚:僕は指導教科の松崎先生の紹介で知りました。いろいろな研究を見てみたいとか、横森さんとかと被りますが、いろいろな方々とコネクションを作りたいと思い参加しました。実際に参加してみると、自分とは違うバックグラウンドの方々と話せたことが自分にとって良い経験になりました。いろいろな分野の研究内容について知ることができ、スライドなども参考になる作り方をされている方がいて勉強になりました。印象に残ったことでは、実機に触れる機会が少なかったのですが、実際に理化学研究所の量子コンピューターに触れることができて良かったです。
渡邉:私も詳しく覚えてないのですが、たしか福島君経由で情報収集しているときに引っかかったような気がしています。僕らのチームは学生がメインでやっていたので、専門家からのフィードバックをいただきたく参加しました。実際に参加してみると、幅広いバックグラウンドの人の発表を聞くことができて、こういう研究もあるんだということが知れて、刺激的でした。また結構厳しい指摘をされている方もいらしたことが印象に残っています。ただ、非常に勉強になるような指摘の仕方でしたので、人に指摘する姿勢や、質問の手法、専門家の方々がどのような点に着目しているのかという視点を知れたことなど、参考になることが多々ありました。
福島:僕はもともとコンパイラの開発に関してはバイト先から人件費といった形でサポートを受けていたのですが、海外の学会に参加する際の渡航費などのサポートは難しく、NQCではそういった用途に使える資金援助を受けることができると聞いて応募しました。また僕も理化学研究所の見学やRAの発表などに参加させていただきましたが、参加されている皆さんが専門家と議論ができるほど、深く高いレベルであると感じ驚きました。量子情報コミュニティに参加していなかった僕たちからすると刺激になったことが印象に残っています。
板橋:所属する研究室から3年か4年連続くらいNQCの探索型に採択されていたこともあり、お薦めしていただき参加することを決めました。実際に参加してみると、自分の分野は量子センサーなんですが、NQCに参加されている方は、量子情報だったり量子情報通信だったり、自分が普通に研究していたら関わらないような分野の方の研究など、色々なことを知ることができてすごく良かったと思います。それから木倉さんの研究なんですけど、僕は研究でJaynes-Cummings modelを扱っているものの、今まで共振器や量子電磁気学に触れたことがなかったのですが、これを機に手を出したいと思うほど面白い発表を聞くことができました。こうした自分では手が出ていなかったところにも出せるようになったことが印象に残りました。
横山:ありがとうございます。板橋君の印象に残ったということで、木倉君いかがでしょうか。
木倉:自分の理論研究について、直接リアクションをいただける機会は多くないので、今日直接そう言っていただけて嬉しいです。
研究に集中できる環境をサポートするNQCプログラムの参加メリットとは?
ここで「体験型」と「探索型」プログラムに参加した江守氏からも自身の経験をもとにした質問があがった。
江守:皆さんのお話を聞いて、NQCの影響力を再確認できました。そして私も「探索型」を応募したきっかけを思い出してみたのですが、金銭面でのサポートという魅力が大きかった気がします。NQC探索型プログラムでは、研究のサポートとして、採択者が研究費(雑所得)を受け取ることができます。そこで、純粋に気になったことなのですが、もし、「探索型」として研究面あるいは私生活面で金銭的なサポートが無くても、「探索型」へ応募していたかどうか教えてください。
木倉:自分は申し込んでいたと思います。実際、研究ではほとんどお金を使っておらず、研究費そのものが目的ではありませんでした。ではなぜ申し込んだのかというと、自身の研究活動に対してフィードバックが得られるプログラムだと期待していたからです。ただ、実際にフィードバックを受ける機会もありましたが、少し限られていたように感じました。修了生の立場から敢えて提案させていただくと、NQC周辺の専門家や他の参加者や修了生など、さらに多くのフィードバックを得る機会が用意されていれば、活動のさらなる充実につながるのではないかとも思います。
江守:よく分かります。自分も理研から給料をいただいているので、当時、「探索型」へ応募を検討していた頃に比べると金銭面はそれほど困っていません。なので、今の状況で「探索型」への応募を検討するとなると、やはり「環境」や「フィードバック」を求めることになると思います。NQC周辺には教員の方々や、修了生たちでも、量子関連のさまざまな専門性を持った方たちもいるので、報告書の共有や相談の機会など、何か連携はもっともてるようになったらいいなと思います。
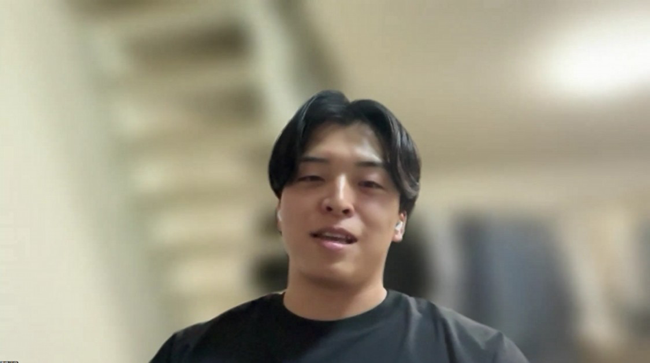
横山:なるほど。木倉くんの考えはよく分かりました。ただやはり学生目線では、アルバイトなどをせず研究に専念できるという意味では金銭の支援っていうのは大事だと思うのですが、そのあたりはいかがですか?
木倉:もちろん、「自由に使えるお金がもらえる」「バイトを減らして研究に集中できる」といった点は学生にとって非常にありがたいことです。この点がきちんとホームページに明記されていれば、非常に魅力的なプログラムではないかと思います。
江守:応募前の段階では「このお金がどう使えるのか」が分かりにくいですよね。きちんと明示されていないので、結局「知っている人に聞く」か「事務局に問い合わせる」しかなくて、私もよく知り合いから質問されます。そうなると、知っている人が有利な"知り合いゲーム"になってしまっている気がします。
横山:了解です。このお話はまずは運営として受け止めさせていただきます。こういった意見を言ってもらえるのがありがたいです。
NQCを起点に、他の取り組みへも積極的に取り組む参加者たち
横山:話しは変わりますが、例えばGraphixの開発などの分野であれば、IPAの未踏プロジェクトなどにも応募できたと思いますが・・・
福島:いま、応募していて審査中です。
横山:なぜ先にNQCに応募したのですか?
福島:少し個人的な事情ですが、最初に知っていたのは未踏の方だったのですが、昨年は修士2年で修論が忙しく、未踏の申請は負担が大きそうだったため見送りました。NQCに応募したのは、ちょうどワークショップへの参加にお金が必要になったタイミングと、NQC期間中に取り組めそうなテーマがあったからです。
横山:なるほど、そうなんですね。実は未踏プロジェクトとは連携を考えていて、昨年度はNQC出身者が4名ほど未踏に参加しています。ぜひ皆さんも良いステップになると思いますので、採択されたら教えてください。
横森:僕も今審査中です。未踏についてはあまり良く知らなかったのですが、うちの研究室のメンバーはよく応募していたとのことで、薦めていただきました。
平塚:僕はあまり考えていなかったです。とりあえず今は基礎を固めてから考えたいと思います。
板橋:これは僕の勘違いかもしれないのですが、未踏のプロジェクトとは、量子コンピューターのプロジェクトのことですよね。僕の場合ですと量子センサーの分野なので、ぜんぜん違っていて、多分未踏のターゲットではないと思うので応募していないです。
江守:その通りだと思います。NQCの良いところは、量子に関係しているものであれば何でも良いっていうぐらいのスタンスですが、未踏は量子の中でも量子コンピューティングを対象としているので、私の分野としては応募しづらい印象です。その点はサービス提供側として知っておくべきで、NQCの事務側でも区別するべきだと思います。
横山:ありがとうございます。立ち位置の違いは意識したいと思っていたので大変参考になります。他の皆さんはいかがですか?NQC以外で、何か外部のイベントや学会などに参加するといったアクションを起こしている人はいますか?
板橋:僕は、学会には以前から参加しています。学会以外では、直近では関東量子スチューデントチャプターに参加しました。
木倉:僕も学会には以前から参加しており、関東量子スチューデントチャプターにも、3年程前から参加しています。
江守:「スチューデントチャプター」という名前になっていますが、学会、ワークショップ、セミナーなどとも言い難い独自の形式になっている気がします。学会は参加費を支払う必要があったり、会員資格を保有している必要があったりするので、参加するハードルが高い気がしますが、もっと気軽に参加できる学生中心の場を、という意図で始まったということを聞いた覚えがあります。また全国規模だと大きすぎるため、関東・関西に分けられて運営されています。関東は研究室や学生数が多いので、参加者も多くなっています。
NQCプログラムの課題とは?
横山:次に、皆さんがNQCのプログラムで課題と感じている点などについて聞かせてもらっても良いですか?
木倉:先ほど話に上がったように、NQC探索型プログラムは研究面や私生活を補う金銭面のサポートとしては、大変充実しています。一方で現状ですと、フィードバックが少ないために自主性を強く持って取り組まなければ順調に活動を進めることが難しいかもしれないと感じました。
横山:はい。その点は我々も問題意識を持っています。
江守:私の時は最初の半年ぐらいは進捗があまりなく、周りをみるとどんどん進んでいて、「自分はこれでいいのかな?」と感じ、自からプレッシャーをかけながらやっていました。このあたりは教育プログラムとして考えて行くべきだと思います。
横山:ありがとうございます。参考になります。他の方はいかがですか?NQCプログラムの課題などについてご意見をいただきたいです。
横森:個人的には、もう少しフィードバックをいただきたかったです。月に1回ぐらいはいただいて、どんどんブラッシュアップしていくイメージを持っていましたが、実際には中間発表と最終発表だけだったので・・・。もう少しメンタリングのようなものがあったら嬉しかったです。
横山:ありがとうございます。メンタリングについては、我々も自覚していて、改善策を模索中です。たとえば、分野を絞って専門の指導者を配置する案や、博士課程の学生などをアルバイト的にメンターとして招き、フィードバックをお願いすることも検討しています。さらに言うと、例えば福島君のように、分野は違うけど応募数の多いテーマを理解している人がレビュー役として関わっていただけるとありがたいです。

福島:はい、僕も積極的にやらせていただきたいと思っています。また実際にNQCはOB/OGも増えていると思うので、制度的にはじめても良い時期だと思います。
板橋:僕も声をかけていただければ、また新しいテーマについて知ることができる良いきっかけになると思うので、ぜひ積極的に参加したいです。
横山:ありがとうございます。
参加者同士のコネクションを深めていくことが、量子研究をさらに進めていくために重要
横山:最後に、これから参加したいという人へのメッセージや今後の展望についてお話しを伺っても良いですか?
平塚:NQCに参加したことで、発表の機会やスライド作成の工夫、周囲のハイレベルな参加者から多くの学びが得られ、発表や交流を通じて得られる刺激は非常に大きかったです。特に、研究室では出会えないような学生や専門家と話せたのは貴重な経験でした。プログラムを通じて、自分ももっと頑張ろうと前向きな気持ちになれたのが大きな変化です。これから参加する方にとっても、視野を広げる良いきっかけになると思います。
板橋:中間発表や最終成果発表会での口頭発表などの経験は大きな学びになりました。特に僕にとっては初めての機会だったので、非常に有意義でした。また、参加者同士のネットワークという面でも、後から思わぬ場で「自分もNQCに参加していた」と話せるようなつながりができたのは良い経験でした。NQCへの参加は、自分の視野を広げる良いチャンスになると思います。
福島:スキルや知識の面では、自分の研究分野とNKCのコミュニティにあまり重なりがなかったため、大きな変化はありませんでした。ただ、期間中に理研の研究者や他の方々と話す機会があり、今後の研究の方向性について考える大きなきっかけになりました。また、学会発表などのアウトプットはこれからですが、顔見知りの研究者が増えたことや、さまざまな分野の人たちの関心や雰囲気を知れたのは大きな収穫でした。これから参加を考えている方にとっても、新しい視点や刺激を得られる貴重な機会になると思います。
横森:すみません。少し話しが脱線しちゃうかもしれないのですが、これから参加する高校生や大学生へ向けて、普段入れないような研究施設やファブ施設の見学など、現場を見て体感する機会を企画しても良いかも知れません。体験することで、量子情報や量子ネットワークといった分野への関心や興味、理解が深まると思います。
江守:先ほどもお話したように、私の場合NQCは費用面などのサポートがあったから、その一歩を踏み出すきっかけになりましたが、プログラム修了後に得られたのは、量子研究に関する横のついながりというか、コミュニティに参加できたことが大きかったと思います。ですので、今後もどこかでお会いする機械があるかと思うので、その時はぜひご飯一緒に行きましょう。それから私が同窓会の幹事もやろうと思っていますので、ぜひ参加してください。皆さんからいろいろとご意見をいただきつつ、さまざまな形で携わっていただければなと思います。今後ともよろしくお願いします。
横山:皆さん、本日はありがとうございました。皆さんのお話しを伺って、NQCを通じて得られるつながりや経験は、一過性のものではなく、これからの研究やキャリアに長く活かせる大きな財産になると感じています。参加者同士のネットワークは思った以上に広く、実際にさまざまな場面で再会したり、会話のきっかけになったりと、目に見えない形で確かに残っていきます。 量子の分野はまだ発展途上で、関わっている人の数も限定されています。その中で、NQCのような場に参加している人たちは、将来的に学術界、産業界などさまざまな立場で再び出会い、自然と横のつながりを持って動ける存在になっていくはずです。「あの時、NQCで出会った」と、みなさんに語ってもらえるような共通の経験が、関係性の土台になっていくと思います。 20年ほど前、僕自身もインターネット技術の研究コミュニティで似たような体験をしました。当時の仲間たちとは今でも仕事上つながっていて、「あの頃の経験が今につながっている」と実感することが多々あります。NQCもまた、そういった未来の礎になり得る場だと信じています。 だからこそ、参加者のみなさんには、NQCを単なるイベントやプロジェクトとして捉えるのではなく、自分の中での出会いや経験を積極的に活用し、大切に育てていってもらえたら嬉しいです。この場を通じて得た関係性や視点が、きっと数年後、思わぬかたちで自分を支える力になるはずです。ぜひ今後も細く長く、関係を続けていければと思います。よろしくお願いします!



